脳卒中リハビリテーション
治療・支援のFirst STEP
[Web動画付]
初めての臨床からわかる・できるステップガイド
![脳卒中リハビリテーション治療・支援のFirst STEP[Web動画付]](../database/cover_image/book/X/ISBN978-4-7583-2091-7.jpg)
定価 5,280円(税込) (本体4,800円+税)

- B5変型判 280ページ オールカラー,イラスト220点,写真250点
- 2023年9月17日刊行
- ISBN978-4-7583-2091-7
電子版
序文
監修の序
皆さん,脳卒中のリハビリテーション医療の世界にようこそ。
この本は,脳卒中のリハビリテーション医療に第一線で携わっている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの療法士の方々を中心に,数名の医師を加え,現在の最先端の脳卒中のリハビリテーション医療をやさしく教えていただくよう執筆をお願いしました。
医療界は,日進月歩のスピードで絶えず新しく更新されてきております。この流れは,リハビリテーション医療の分野でも決して例外ではなく,欧米諸国ではエビデンスを基盤にしたリハビリテーション治療が展開され,大きなうねりとなって押し寄せてきています。第一線で活躍されている療法士の方々は絶えず,そのうねりを肌に感じながら日々の診療に従事しているのですが,急速に進化していく脳卒中のリハビリテーション医療に取り残されてしまうのではないかと絶えず危惧しているのが現状です。一方で,療法士を養成している学校では,最新とは言い難いことを記述している教科書を使用しているところも多く,ひと昔前の脳卒中のリハビリテーション医療しか教えていないところが多いのもまた現状です。
こういった現状を打破すべく,志を同じくした第一線で活躍している筆者たちがここに結集し,『脳卒中リハビリテーション治療・支援のFirst STEP』を書き上げました。まさに,この本を「first step」として,学生の皆様は勿論,リハビリテーション医学・医療を目指す若い医師,理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・義肢装具士の療法士の皆様,現在の脳卒中のリハビリテーション医療がどのように変わってきているのか知りたい(今さら,周囲の後輩には聞けない世代の)ベテランや中堅療法士の皆様にも是非,手に取って,ひも解いていただきたい書籍です。そして,この書籍を読んだ皆様が,次へのstepにつなげていくことが,脳卒中の後遺障害で苦しむ患者さんや多くの障害児者,高齢者のよりよい生活を支えていくことにつながると確信します。
皆さんとともに本を「first step」として,日本の脳卒中のリハビリテーション医療を大いに発展させて,脳卒中後遺障害で悩む患者さんへの一条の光明となることができれば幸いです。
2023年8月
昭和大学リハビリテーション医学講座
川手信行
----------------------------------
編集の序
私は2011年4月に現職の荏原病院に入職しました。本書を執筆した時点で臨床13年目の理学療法士です。共同編集した栗田慎也先生との出会いは,2014年の夏ごろに中途採用で荏原病院に入職してきたところから始まります。
今思えば,私が彼と出会う前までの脳卒中のリハビリテーション治療ははっきり言って褒められたものではありませんでした。やっていたことといえば,早期離床くらいで,早期に離床させることだけに注力していました。また,リハ室に来てもベッド上で寝ている時間が多く,歩行トレーニングといえば平行棒内で数回行う程度でした。患者は良くならないことも実感していましたし,生活期にボツリヌス療法で来院した患者の多くは麻痺が回復せず,痙縮が出現し,痛みも訴え,ウェルニッケ・マン肢位となり,とても長くは歩けない非効率な揃え方の歩行で来院されていました。この現状は私にとってとても心苦しいものでした。「どうにかできないのか? 本当にこのままで良いのか?」自問自答を繰り返す日々でした。
しかし,彼との出会いが一つのターニングポイントでした。回復期リハビリテーション病院から転職してきた彼は,当院の倉庫に眠っていた長下肢装具を引っ張り出し,患者を立たせ,後方介助で歩行トレーニングを開始しました。彼が歩行トレーニングを行った患者の反応など,私が経験したことのないものでした。その時,私は彼に「教えてくれ!」と言って,自分の患者に長下肢装具を装着して介助方法の手ほどきを受けました。
そこから,栗田慎也先生と二人で当院の脳卒中リハビリテーション治療を見直すことが始まりました。運動麻痺を治療するためにはステージ理論に依拠すること。そこには電気刺激治療などの刺激入力が重要で,さまざまな治療デバイスを使いこなす必要があること。また,長下肢装具などを使用して早期から立位歩行練習を行う際には肩を保護することや低栄養などのリスク管理をしっかり行うこと。これらを職場内に広めて実践し,外部に発信し,自分たちの行っていることが正しいのか確認していくこと。その中には逆風も多くありましたが,二人三脚で歩んできました。
そしてもう一つ,大きな出会いは監修を務めていただいた川手信行先生です。川手先生は「急性期・回復期は長くても6カ月。患者の人生は6カ月よりはるかに長く続く。そこを考えなさい」と教えてくださいました。急性期リハビリテーションに注力していた我々に大きな衝撃でした。このことは,急性期で治療した患者をしっかり生活期までフォローすること,決して急性期・回復期だけやればいいってもんじゃないと一喝された思いでした。生活期の装具の諸問題や住環境,復職支援,自動車運転,これらに関わる法律や制度,当事者の思いを理解しなければならないと教わりました。
これらの経験をもとに本書は特に急性期・回復期で脳卒中リハビリテーション治療に必要なエッセンスを各先生方にご執筆いただきました。エッセンスのみを執筆してほしいがゆえに執筆者の先生方には慣れない執筆方法で大変ご迷惑をおかけしたと思います。この場を借りて,お詫びと感謝を申し上げます。
本書籍の表紙は,ファーストペンギンを意味します。ファーストペンギンとは元来臆病なペンギンの中で,多くの敵が潜む海に最初に飛び込み,仲間たちを先導する「勇気ある一羽目のペンギン」を指します(Wikipediaより)。私は2023年現在,さまざまなテクノロジーやエビデンスが出ているのにもかかわらず,臨床現場に取り入れられず,患者に還元されていないように感じています。どうか,本書を手に取った皆様がファーストペンギンとなり,この現状を打破して,脳卒中患者のより良い人生のためにお役立ていただければ幸甚に思います。また,本書をFirst Stepの一歩目として,より深く学会や論文,詳述された成書で学んでいただければと思います。
最後になりますが,当院リハビリテーション科部長の尾花正義先生には実臨床や本書をはじめとしていつも多くのご指導をいただき,感謝いたします。そして,監修を務めていただいた昭和大学医学部リハビリテーション医学講座主任教授の川手信行先生には的確なアドバイスをいただき深く感謝いたします。また,最後まで親身にご相談に乗っていただいたメジカルビュー社 第二編集部の間宮卓治氏に感謝いたします。
2023 年8月
髙橋忠志
皆さん,脳卒中のリハビリテーション医療の世界にようこそ。
この本は,脳卒中のリハビリテーション医療に第一線で携わっている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの療法士の方々を中心に,数名の医師を加え,現在の最先端の脳卒中のリハビリテーション医療をやさしく教えていただくよう執筆をお願いしました。
医療界は,日進月歩のスピードで絶えず新しく更新されてきております。この流れは,リハビリテーション医療の分野でも決して例外ではなく,欧米諸国ではエビデンスを基盤にしたリハビリテーション治療が展開され,大きなうねりとなって押し寄せてきています。第一線で活躍されている療法士の方々は絶えず,そのうねりを肌に感じながら日々の診療に従事しているのですが,急速に進化していく脳卒中のリハビリテーション医療に取り残されてしまうのではないかと絶えず危惧しているのが現状です。一方で,療法士を養成している学校では,最新とは言い難いことを記述している教科書を使用しているところも多く,ひと昔前の脳卒中のリハビリテーション医療しか教えていないところが多いのもまた現状です。
こういった現状を打破すべく,志を同じくした第一線で活躍している筆者たちがここに結集し,『脳卒中リハビリテーション治療・支援のFirst STEP』を書き上げました。まさに,この本を「first step」として,学生の皆様は勿論,リハビリテーション医学・医療を目指す若い医師,理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・義肢装具士の療法士の皆様,現在の脳卒中のリハビリテーション医療がどのように変わってきているのか知りたい(今さら,周囲の後輩には聞けない世代の)ベテランや中堅療法士の皆様にも是非,手に取って,ひも解いていただきたい書籍です。そして,この書籍を読んだ皆様が,次へのstepにつなげていくことが,脳卒中の後遺障害で苦しむ患者さんや多くの障害児者,高齢者のよりよい生活を支えていくことにつながると確信します。
皆さんとともに本を「first step」として,日本の脳卒中のリハビリテーション医療を大いに発展させて,脳卒中後遺障害で悩む患者さんへの一条の光明となることができれば幸いです。
2023年8月
昭和大学リハビリテーション医学講座
川手信行
----------------------------------
編集の序
私は2011年4月に現職の荏原病院に入職しました。本書を執筆した時点で臨床13年目の理学療法士です。共同編集した栗田慎也先生との出会いは,2014年の夏ごろに中途採用で荏原病院に入職してきたところから始まります。
今思えば,私が彼と出会う前までの脳卒中のリハビリテーション治療ははっきり言って褒められたものではありませんでした。やっていたことといえば,早期離床くらいで,早期に離床させることだけに注力していました。また,リハ室に来てもベッド上で寝ている時間が多く,歩行トレーニングといえば平行棒内で数回行う程度でした。患者は良くならないことも実感していましたし,生活期にボツリヌス療法で来院した患者の多くは麻痺が回復せず,痙縮が出現し,痛みも訴え,ウェルニッケ・マン肢位となり,とても長くは歩けない非効率な揃え方の歩行で来院されていました。この現状は私にとってとても心苦しいものでした。「どうにかできないのか? 本当にこのままで良いのか?」自問自答を繰り返す日々でした。
しかし,彼との出会いが一つのターニングポイントでした。回復期リハビリテーション病院から転職してきた彼は,当院の倉庫に眠っていた長下肢装具を引っ張り出し,患者を立たせ,後方介助で歩行トレーニングを開始しました。彼が歩行トレーニングを行った患者の反応など,私が経験したことのないものでした。その時,私は彼に「教えてくれ!」と言って,自分の患者に長下肢装具を装着して介助方法の手ほどきを受けました。
そこから,栗田慎也先生と二人で当院の脳卒中リハビリテーション治療を見直すことが始まりました。運動麻痺を治療するためにはステージ理論に依拠すること。そこには電気刺激治療などの刺激入力が重要で,さまざまな治療デバイスを使いこなす必要があること。また,長下肢装具などを使用して早期から立位歩行練習を行う際には肩を保護することや低栄養などのリスク管理をしっかり行うこと。これらを職場内に広めて実践し,外部に発信し,自分たちの行っていることが正しいのか確認していくこと。その中には逆風も多くありましたが,二人三脚で歩んできました。
そしてもう一つ,大きな出会いは監修を務めていただいた川手信行先生です。川手先生は「急性期・回復期は長くても6カ月。患者の人生は6カ月よりはるかに長く続く。そこを考えなさい」と教えてくださいました。急性期リハビリテーションに注力していた我々に大きな衝撃でした。このことは,急性期で治療した患者をしっかり生活期までフォローすること,決して急性期・回復期だけやればいいってもんじゃないと一喝された思いでした。生活期の装具の諸問題や住環境,復職支援,自動車運転,これらに関わる法律や制度,当事者の思いを理解しなければならないと教わりました。
これらの経験をもとに本書は特に急性期・回復期で脳卒中リハビリテーション治療に必要なエッセンスを各先生方にご執筆いただきました。エッセンスのみを執筆してほしいがゆえに執筆者の先生方には慣れない執筆方法で大変ご迷惑をおかけしたと思います。この場を借りて,お詫びと感謝を申し上げます。
本書籍の表紙は,ファーストペンギンを意味します。ファーストペンギンとは元来臆病なペンギンの中で,多くの敵が潜む海に最初に飛び込み,仲間たちを先導する「勇気ある一羽目のペンギン」を指します(Wikipediaより)。私は2023年現在,さまざまなテクノロジーやエビデンスが出ているのにもかかわらず,臨床現場に取り入れられず,患者に還元されていないように感じています。どうか,本書を手に取った皆様がファーストペンギンとなり,この現状を打破して,脳卒中患者のより良い人生のためにお役立ていただければ幸甚に思います。また,本書をFirst Stepの一歩目として,より深く学会や論文,詳述された成書で学んでいただければと思います。
最後になりますが,当院リハビリテーション科部長の尾花正義先生には実臨床や本書をはじめとしていつも多くのご指導をいただき,感謝いたします。そして,監修を務めていただいた昭和大学医学部リハビリテーション医学講座主任教授の川手信行先生には的確なアドバイスをいただき深く感謝いたします。また,最後まで親身にご相談に乗っていただいたメジカルビュー社 第二編集部の間宮卓治氏に感謝いたします。
2023 年8月
髙橋忠志
全文表示する
閉じる
目次
第1章 苦手を克服! 画像のみかた!【大村優慈】
脳画像ってなんで重要なの?
中枢神経の機能解剖
脳画像のみかた
CTとMRIの違い(撮影時間,出血,梗塞,時間的変化)
拡散テンソルトラクトグラフィーってなに?
脳画像からみる機能予後
第2章 脳卒中の病態・疫学・治療【近 貴志】
脳卒中の病態・疫学・治療
第3章 運動麻痺を治療する!【髙橋忠志,栗田慎也,唐渡弘起】
運動麻痺総論
拘縮と痙縮
運動失調
米国STEP会議
不動はなぜだめなのか?
治療の根幹,早期離床(エビデンス・リスク管理)
ステージ理論
皮質脊髄路を興奮させる
課題指向型トレーニングと機能指向型トレーニング
運動学習の原則(1) Fire together,wire together
運動学習の原則(2) 褒める
第4章 治療デバイスを使いこなす【中村 学,唐渡弘起,林 翔太,勝平純司,松田雅弘】
電気刺激治療総論
NMES
TENS
FES
IVES
上肢装具(肩装具・スプリント)
上肢麻痺に電気刺激を使う
上肢ロボット
ニューロモジュレーション
半球間抑制ってなに?
EMGBF
VRってどう活用するの?
第5章 歩行を獲得せよ!【勝平純司,髙橋忠志,栗田慎也,中村 学,村山 稔】
正常歩行のバイオメカニクスと筋活動,歩行の評価
ロッカー機能と振子運動
歩行障害に対するリハビリテーション治療
長下肢装具を使う
トレッドミルで歩く
免荷式歩行トレーニング
歩行トレーニングで電気刺激を使う
歩行ロボット
歩行能力の回復と下肢装具の設定
歩行パターンと短下肢装具の適応
Gait solutionってどう使うの?
Extension thrust pattern(反張膝)の治療
Stiff-knee gaitの治療
第6章 「動作分析が苦手です」はこの章で卒業しよう【林 翔太,勝平純司,大田瑞穂】
苦手意識を克服! 観察による動作分析!
寝返り
起き上がり
起立・着座
階段昇降
第7章 姿勢制御とバランスって理解してる?【松田雅弘】
バランス障害の評価と治療
pusher,lateropulsionの違い
第8章 高次脳機能障害の苦手意識を克服!【藤野雄次】
半側空間無視・注意障害の病態と評価・治療
病態失認・身体失認の病態と評価・治療
失行の病態と評価・治療
認知症? せん妄? 失語症? の違い
第9章 腹が減っては運動はできぬ!【最上谷拓磨,齋藤真由】
脳卒中の栄養評価
サルコペニア・フレイル
脳卒中の栄養療法
摂食嚥下障害の病態と評価
嚥下調整食とその功罪
摂食嚥下のリハビリテーション治療
第10章 脳卒中のリハビリテーション支援【河添竜志郎,君浦隆ノ介,澤田辰徳,勝谷将史】
生活環境の整備(福祉用具・住宅改修)
復職・就労支援
自動車運転支援
医療保険,介護保険,障害者総合支援法,保険外リハビリテーション支援
治療用装具と更生装具
コラム
Wake up! 覚醒せよ!
皮質網様体路の経路と機能的役割
施設間の情報共有の重要性
当事者がセラピストに思うこと
ボツリヌス治療
痛みはリハビリテーション治療を止める?! 脳卒中後疼痛について
論文の読み方
KAFOはいつまで使うのか? カットダウンの指標
生活期の装具諸問題について
リハビリテーション治療の時間だけ動いてませんか? 21時間の身体活動
MDCとMCIDってなに?
足趾屈曲への対応
CB-KAFO
情報収集と情報発信(情報リテラシーとは)
記憶障害
遂行機能障害
失語症の分類
食べるも大事! 出すのも大事! 下痢と便秘!
エビデンスに基づくって?
レスポンダー・ノンレスポンダーとは?
目指すチーム医療の形とは?
脳卒中リハビリテーション医療に関わる職種
脳画像ってなんで重要なの?
中枢神経の機能解剖
脳画像のみかた
CTとMRIの違い(撮影時間,出血,梗塞,時間的変化)
拡散テンソルトラクトグラフィーってなに?
脳画像からみる機能予後
第2章 脳卒中の病態・疫学・治療【近 貴志】
脳卒中の病態・疫学・治療
第3章 運動麻痺を治療する!【髙橋忠志,栗田慎也,唐渡弘起】
運動麻痺総論
拘縮と痙縮
運動失調
米国STEP会議
不動はなぜだめなのか?
治療の根幹,早期離床(エビデンス・リスク管理)
ステージ理論
皮質脊髄路を興奮させる
課題指向型トレーニングと機能指向型トレーニング
運動学習の原則(1) Fire together,wire together
運動学習の原則(2) 褒める
第4章 治療デバイスを使いこなす【中村 学,唐渡弘起,林 翔太,勝平純司,松田雅弘】
電気刺激治療総論
NMES
TENS
FES
IVES
上肢装具(肩装具・スプリント)
上肢麻痺に電気刺激を使う
上肢ロボット
ニューロモジュレーション
半球間抑制ってなに?
EMGBF
VRってどう活用するの?
第5章 歩行を獲得せよ!【勝平純司,髙橋忠志,栗田慎也,中村 学,村山 稔】
正常歩行のバイオメカニクスと筋活動,歩行の評価
ロッカー機能と振子運動
歩行障害に対するリハビリテーション治療
長下肢装具を使う
トレッドミルで歩く
免荷式歩行トレーニング
歩行トレーニングで電気刺激を使う
歩行ロボット
歩行能力の回復と下肢装具の設定
歩行パターンと短下肢装具の適応
Gait solutionってどう使うの?
Extension thrust pattern(反張膝)の治療
Stiff-knee gaitの治療
第6章 「動作分析が苦手です」はこの章で卒業しよう【林 翔太,勝平純司,大田瑞穂】
苦手意識を克服! 観察による動作分析!
寝返り
起き上がり
起立・着座
階段昇降
第7章 姿勢制御とバランスって理解してる?【松田雅弘】
バランス障害の評価と治療
pusher,lateropulsionの違い
第8章 高次脳機能障害の苦手意識を克服!【藤野雄次】
半側空間無視・注意障害の病態と評価・治療
病態失認・身体失認の病態と評価・治療
失行の病態と評価・治療
認知症? せん妄? 失語症? の違い
第9章 腹が減っては運動はできぬ!【最上谷拓磨,齋藤真由】
脳卒中の栄養評価
サルコペニア・フレイル
脳卒中の栄養療法
摂食嚥下障害の病態と評価
嚥下調整食とその功罪
摂食嚥下のリハビリテーション治療
第10章 脳卒中のリハビリテーション支援【河添竜志郎,君浦隆ノ介,澤田辰徳,勝谷将史】
生活環境の整備(福祉用具・住宅改修)
復職・就労支援
自動車運転支援
医療保険,介護保険,障害者総合支援法,保険外リハビリテーション支援
治療用装具と更生装具
コラム
Wake up! 覚醒せよ!
皮質網様体路の経路と機能的役割
施設間の情報共有の重要性
当事者がセラピストに思うこと
ボツリヌス治療
痛みはリハビリテーション治療を止める?! 脳卒中後疼痛について
論文の読み方
KAFOはいつまで使うのか? カットダウンの指標
生活期の装具諸問題について
リハビリテーション治療の時間だけ動いてませんか? 21時間の身体活動
MDCとMCIDってなに?
足趾屈曲への対応
CB-KAFO
情報収集と情報発信(情報リテラシーとは)
記憶障害
遂行機能障害
失語症の分類
食べるも大事! 出すのも大事! 下痢と便秘!
エビデンスに基づくって?
レスポンダー・ノンレスポンダーとは?
目指すチーム医療の形とは?
脳卒中リハビリテーション医療に関わる職種
全文表示する
閉じる
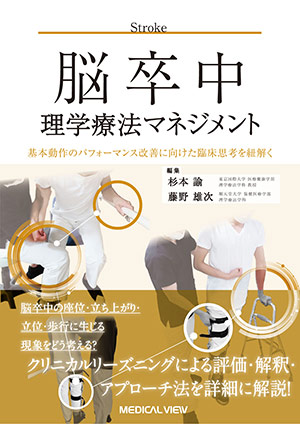
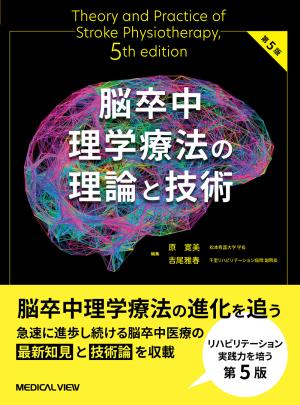
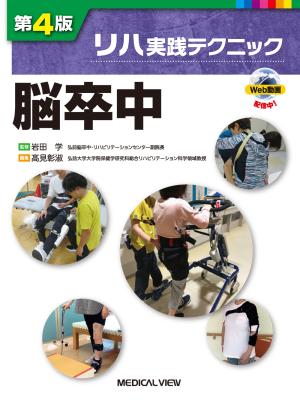
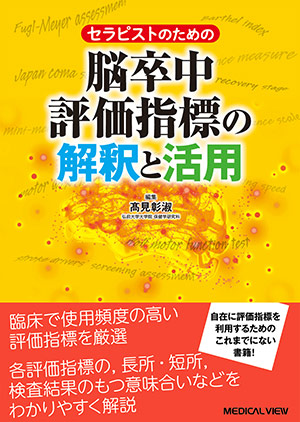

最初の一歩を踏み出すためのエッセンスを集約,実臨床で活きるテクニックと理論をわかりやすく解説! 実践動画付き
PT・OT の初学者向けに,脳卒中回復のステージ理論や脳画像重視など,現在最新の情報に基づいて脳卒中リハを手がけるために必要な情報を厳選。
オールカラー紙面に写真やイラストを多用してビジュアルに解説し,デバイスの使い方や装具の装着などの様子を動画でも参照可能。
さらに「情報収集と情報発信」「施設間の情報共有の重要性」など,将来のキャリアパス形成に役立つ情報を紹介するコラムも満載。
“かゆい所に手が届く”実臨床で活きる一冊!